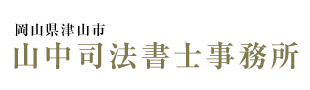相続手続きの流れ相続が発生したら、まず戸籍謄本の収集から行います
相続人の調査
相続が発生すると、まず一番最初にするべきことは、法律で定める相続人(法定相続人)が誰であるのか調査することです。相続人なんて調べなくてもわかるという方も多いですが、 法務局や金融機関などにおいては、戸籍謄本や法定相続情報一覧図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)や預金を解約することができません。 そのため、相続が発生したら、まず戸籍謄本の収集(相続人の調査)から行います。
相続財産の内容の確認
不動産や、預金・株式・国債などの金融資産が一般的な相続財産となります。 相続においては、「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も相続の対象となります。相続財産のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合などは、相続放棄や限定承認など家庭裁判所での手続を視野に入れることも必要です。
また近年、債務はなくても、売れる見込みもなく、撤去費もかかる空き家を相続したくないがために、相続放棄をする人も増加しています。
ただ相続人全員が相続放棄し、相続人が存在しなくなると、相続放棄した人にも管理責任が残るので要注意です。
遺言の有無の確認
遺産分割を行う前に、亡くなられた方が遺言書を残しているかどうか確認する必要があります。有効な遺言書がある場合、原則その内容が最も優先されます。
遺産分割協議
遺言書がない場合、通常は被相続人の財産を相続人間でどのように分割するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をした結果、分割する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
遺産の名義変更手続など
上記、遺産分割協議、遺言の内容に従い、各遺産の名義変更、解約などを行います。相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、不動産の名義変更の登記(相続登記)をします。
相続登記の申請が義務化法改正により2024年4月1日から
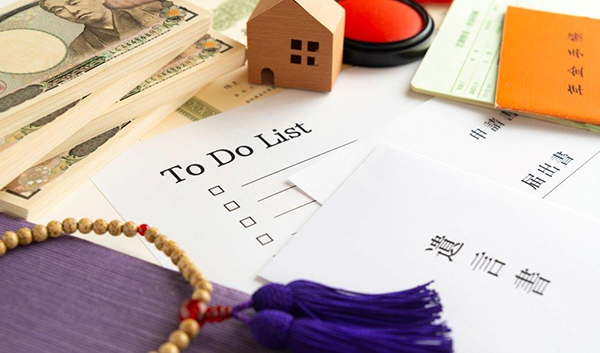
相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
- 相続登記必要書類
-
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(亡くなられて長期間経っている場合は発行されないこともあります)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産名義人になる方の住民票
- 今年度の不動産の評価額の記載された書面(最新年度のもの 納税通知書、名寄帳、評価証明書等)
※不動産の名義人になる方の免許証等の本人確認書類の提示をお願いしています。
※印鑑証明書以外は司法書士が代理して取得することができます。
※代襲相続・数次相続が発生している場合は、中間の相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
※被相続人の配偶者(妻または夫)が被相続人より後に死亡している場合は、その配偶者の出生から婚姻までの戸籍謄本が必要となります。
※被相続人の登記簿上のご住所と最後のご住所地が異なる場合は、被相続人の登記済証(権利証)が必要になる場合があります。